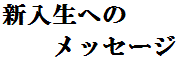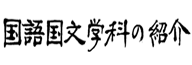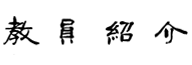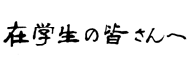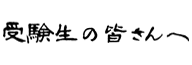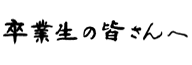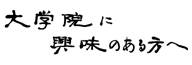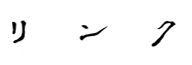■教員紹介(2)
中国文学
谷口 高志(たにぐち たかし)
Taniguchi,Takashi
教育・総合科学学術院 准教授
◆専門分野
中国古典文学、特に唐代の文学。
◆略歴
大阪府出身。大阪大学文学部卒業。
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。
2011年、大阪大学大学院文学研究科助教。
2013年、佐賀大学文化教育学部講師。
2015年、同准教授。
2016年、佐賀大学教育学部准教授。
2017年、佐賀大学教育研究院人文・社会科学域教育学系准教授。
2025年、早稲田大学教育・総合科学学術院准教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
中国前近代の文学のうち、特に関心を寄せているのは中唐期(唐代の文学を四つに時代区分したうちの一つ)の詩文です。この時代は中国文学史上の一大変革期にあたり、それまでになかった新たな潮流が様々なかたちで見られるようになります(その変化は「唐宋変革」といわれる中国史の大きな流れとも連動しています)。たとえば詩歌の主題として、詩人たち自身の日常生活が盛んに詠われるようになるのはこの時期からですし、恋愛を扱った小説が書かれ出すのもこの時期です。こうした中唐文学の〈新しさ〉は、現代を生きる我々の日常とも遠く響き合っているところがあり、過去のテクストを掘り起こしながら、自分のなかに内在化されている価値観や規範意識を見つめ直すことに喜びを感じています。最近では、科挙について語った詩文に着目し、科挙受験が人々の生活様式に与えた影響や、それに伴う価値観の変化について再検討してみようと思っています。
◆主な著書・論文
『中国文学のチチェローネ──中国古典歌曲の世界』(2009年、汲古書院、分担執筆)
『皇帝のいる文学史──中国文学概説』(大阪大学出版会、2015年、共編著)
『元典章が語ること──元代法令集の諸相』(2017年、大阪大学出版会、共編著)
「唐詩の音楽描写──その類型と白居易「琵琶引」」(『日本中国学会報』第56号、2004)
「愛好という病──唐代における偏愛・偏好への志向」(『東方学』第126号、2013)
「白居易・元稹の祝文とその周辺──唐代の祝文系作品における地方官と神霊・怪異(上)」(『九州地区国立大学教育系・文系研究論文集』第9巻第1号、2022)
◆教員からの一言
残念ながら漢文は国語科のなかでも特に人気がある分野ではありません。学生の皆さんのなかにも、こう思っている人がいるかもしれません。なぜ、いま使われていない昔の言葉、しかも外国由来のものを学校で学ばなければならないのか、と。しかし私は、古典であること(現代語でないこと)、そして外国語であること、この二つが、我々の〈国語〉を相対化する、つまり第三者の視点で捉えなおす重要な契機となるのではないかと考えています。〈国語〉について、もっと言えば言語表現の規範性と可能性について考えるうえで、『論語』の一節や『史記』の叙述、また杜甫の詩や柳宗元の散文は多くの示唆を与えてくれるように思います。もちろん言語についてだけではなく、人生そのものについても。
内山 精也(うちやま せいや)
UCHIYAMA,Seiya
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
中国古典文学、とくに宋代(960-1279)の詩人と詩歌。
日本の近世・近代における宋代詩歌の受容
「漢文」という教科の成立とその背景
◆略歴
新潟県出身。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院文学研究科退学。
1995年、横浜市立大学講師。
1999年、早稲田大学教育学部講師。
2000年、同助教授。
2006年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
中国の近世が始まる時代とされる宋代の詩人と詩歌を主たる研究対象としています。宋代を代表する詩人は、一般に「士大夫」と称され、科挙に優秀な成績で及第した官僚です。彼らは、国教たる儒学の経典解釈にも画期的な新風を巻き起こしました。宋代詩人の多くが「官僚―学者―詩人」という三つの顔を持ち、その三つの顔が相互に影響し合って一つの人格や個性をつくり出しています。こういう視点に立って、総合的に宋代の詩人たちにアプローチしています。また、宋代は、メディア革命の起こった時代でもあります。木版印刷が急速に普及し、各種情報の発信・受信形態に多大な変化が生まれました。こういう急激な変化の中で、もっとも伝統的な表現形式の一つ「詩」は、どのような影響を受けたのか、これが、今もっとも関心のあるテーマです。
◆主な著書・論文
『傳媒與眞相―蘇軾及其周圍士大夫的文學―』(上海古籍出版社、2005年、中国語)
『蘇軾詩研究 宋代士大夫詩人の構造』(研文出版、2010年)
『廟堂与江湖 宋代詩学的空間』(復旦大学出版社、2017年、中国語)
『宋詩惑問 宋詩は「近世」を表象するか?』(研文出版、2018年)
◆教員からの一言
「外から日本を考える」
国語国文学科の授業内容は、日本語に関わる諸現象を対象としていますから、日本国内に身を置くことで、ただちに最高の学習条件と環境とを獲得することができます。つまり、皆さんはいながらにして学習と研究のための無数の特権と恩恵を得ていることになります。でも、対象が身近かすぎるために、かえって樣々な「常識」に絡め取られ、多くの盲点が生まれやすい危険性も無数に横たわっています。
四年の間に一度は国外に身を置いて、外側から日本を眺め、日本に思いをめぐらせてみませんか。海外に身を置くと、今まで常識と信じて疑わなかったことが、音をたてて崩れる瞬間を、数多く体験することになるはずです。「廬山(ろざん)の真面目(しんめんもく)を識(し)らざるは、只(た)だ身 (み)の此(こ)の山中(さんちゅう)に在(あ)るに縁(よ)る」――山の真の姿を知ろうとするならば、山の中に身を置いていては分からない、山を外側から眺めなければならない、という蘇東坡の名言があります。
対象を客体化し、相対化することは研究の第一歩です。そして、たった三、四時間、飛行機に乗れば、日本を相対化する条件がにわかに生まれます。ぜひ、トライしてみて下さい。
■日本語学
松木 正恵(まつき まさえ)
MATSUKI,Masae
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
日本語学(特に、現代日本語の文法、語彙・意味、文章・談話等の研究)
日本語教育(特に、文型・文法教育、教材等の研究)
◆略歴
出生地は宮城県仙台市。その後父親の転勤で、山形・東京・京都・福岡・長崎等を転々とし、出身高校は長崎県立佐世保南高等学校。
東京学芸大学を卒業後、都立高校教諭を経て、早稲田大学大学院文学研究科博士前期課程修了。
1987年、青森明の星短期大学専任講師。
1989年、早稲田大学日本語研究教育センター助手。
1993年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学、早稲田大学教育学部助手。
1994年、早稲田大学教育学部専任講師。
1997年、同助教授。
2004年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
私達が母語として無意識に身につけてきた日本語を客観的に捉え直すことで、隠れた法則性を発見する――これが、文法研究の醍醐味です。私は、現代日本語の書き言葉・話し言葉を資料として、「複合辞」(幾つかの語が複合して助詞・助動詞的になった表現。例えば「なければならない」「について」等)の機能、文法化のしくみ、連体修飾の構造、視点と文法研究とのかかわり、文法論における引用表現・話法、等を分析しながら、日本語教育にも役立つ文法記述を模索しています。授業でも、"文法は暗記ではなく、発見するもの"をスローガンに、データの収集・分析・考察を通じて、"母語再発見"を体験してもらっています。
◆主な著書・論文
『日本語表現文型―用例中心・複合辞の意味と用法―』(アルク 1989年)
「視点と文体―引用構造を用いた文体の特徴―」(『表現と文体』明治書院 2005年)
「複合辞研究と文法化―動詞が欠落した口語的複合辞を例として―」(『複合辞研究の現在』和泉書院 2006年)
「連体修飾節における底名詞の性質と名詞性接続成分 連体複文構文と連用複文構文の接点を求めて」
(『日本語複文構文の研究』ひつじ書房 2014年)
「連体修飾節の構造と意味 両者のずれから見た節のタイプの連続性」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第2冊 言葉のはたらき』ひつじ書房 2021年)
『複合辞研究 その成り立ちと広がり』(ひつじ書房 2023年)
◆教員からの一言
日本語学が対象とする時代は、日本語を記録した言語資料が現れる上代から、私達が日々言語活動を行っている現代にわたります。また、扱っている言語要素は、音声音韻・文字表記・語彙・文法・文章(書き言葉)・談話(話し言葉)と幅広く、かつ、研究方法も通時的(歴史的)に見るか共時的(同時代的)に見るかで全く異なってきます。さらに、文体や表現の研究、方言・待遇表現(敬語)などの社会言語学的領域や、言語行動・言語生活研究はもちろんのこと、意味論・語用論・認知言語学・対照言語学などとも深い関わりを持っています。一方、日本語教育は、これらの日本語学諸領域に加えて、日本文化や教育学に対する知見も必要不可欠になります。日本語学の広くて深い領域に触れながら、日本語を、「国語」としてではなく、世界の言語の一つとして客観的に見つめ直してみませんか。まるでパズルを解くような面白さに、わくわくすること請け合いです。
仁科 明(にしな あきら)
NISHINA,Akira
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
日本語学・日本語史(特に文法に関する分野)
◆略歴
静岡県出身。
2000年、静岡県立大学国際関係学部専任講師
2007年、静岡県立大学国際関係学部准教授
2010年、早稲田大学教育・総合科学学術院准教授
2014年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授(現職)
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
もともとは現代共通語の文法に関心を持って研究を始めましたが、述語形式や条件表現の意味・用法を考えているうち、対象が古代語に広がってきました。どの時代をあつかう場合でも、多くの意味・用法をもった形式について、意味・用法間のつながりを考えることに一番の関心があります。現在は、古代語の述語形式の研究が中心になっていますが、現代語への興味も持続しています。
◆主な論文
「終止なり」の上代と中古―体系変化と成員(青木博史(編)『日本語の構造変化と文法化』ひつじ書房、2007年7月)
人と物と流れる時と―喚体的名詞一語文をめぐって―(森雄一ほか(編)『ことばのダイナミズム』くろしお出版、2008年9月)
「存在」と「痕跡」―万葉集の「り」「たり」について―(「国語と国文学」86巻11号、2009年11月)
「無色性」と「無標性」―万葉集運動動詞の基本形終止、再考―(「日本語文法」14巻2号、2014年9月)
「属性」と「統覚」とそのあいだ―中間的複語尾の位置づけ―(『日本語文法史研究2』ひつじ書房、2014年10月)
◆教員からの一言
古代の日本語は、現代共通語とのあいだに、厳密には連続性と言えぬまでも強い関連性の指摘できる言語であり、比較をおこなう対象としても恰好のものだといえます。もちろん、両者には、同一の部分や並行する部分も、相違する部分も指摘できるのですが、前者(並行する部分)を観察することからは日本語に特有の発想法のようなものが、後者(相違する部分)を観察することからは現代共通語の特殊性のようなものが、それぞれ浮かび上がってきます。私たちが当然のものだと思っている現在の日本語のあり方を相対化し、その性質を明確にするためにも、古代の日本語を見つめてみる、という経験は重要なものだと思います。
■国語教育
幸田 国広(こうだ くにひろ)
KOUDA, Kunihiro
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
国語教育の理論と実践
国語教育史、表現指導論、文学教育論、教科構造論
◆略歴
東京都出身。法政大学文学部卒業。
早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。
1990年、法政大学第二中学・高等学校教諭。
2008年、東洋大学文学部准教授。
2015年、早稲田大学教育・総合科学学術院准教授
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
主な研究領域は国語教育史研究です。特に、戦後の高等学校における国語科の教科構造について、
教育課程・教科書・授業実践の三層を重ねて、その歴史展開を究明してきました。現在はその延長で国語教科書教材史研究を、
いわゆる「定番教材」の形成過程の解明に焦点をあてて系統的に取り組んでいます。
「ごんぎつね」「走れメロス」「羅生門」等、「定番教材」といわれる一群の教材について、その内容的な特徴だけでなく、
教科書採録に働くさまざまな力学、政治的経済的な外部の文脈との関連等から読み解き、
「定番」という価値の内実とそこに依拠する教育現場の問題性を炙り出そうと努めているところです。
さらに、教科書教材史を内側から支えている国語教育思想の特徴、その基底に働く「読むこと」の思想史にまで探求のアンテナを伸ばそうとしています。
◆主な著書・論文
共著『日本語表現のレッスン』(教育出版 2003年)
編著『益田勝実の仕事5 国語教育論集成』(筑摩書房 2006年)
共編著『国語教育を国際社会へ拓く』(渓水社 2008年)
『高等学校国語科の教科構造 戦後半世紀の展開』(渓水社 2011年)
共編著『教職エッセンシャル』(学文社 2013年)
◆教員からの一言
実践研究についても旺盛に展開したいと考えています。特に、表現指導分野の教材開発、指導法開発は、現在、初等教育においては一定の進展が見られますが、中等教育段階、とりわけ高等学校では依然として低調です。現場からは「必要性はわかるが授業に自信が持てない」「どのように指導すればよいのかわからない」等の声を聞きます。こうした現場の潜在的な要求に応えていくのが国語教育研究に携わる研究者の役割と思っています。教科書編集、ラジオ・テレビの番組制作の中で培ってきた経験を生かし、現場の先生方と共同で実践研究を進めようとしています。
菊野 雅之(きくの まさゆき)
KIKUNO, Masayuki
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
国語科教育
◆略歴
横浜国立大学大学院教育学研究科修了
早稲田大学大学院博士後期課程単位取得満期退学
東京都内の私学中学高校の国語科時間講師を担当
早稲田大学教育・総合科学学術院助手
国立教育政策研究所学力調査専門職
北海道教育大学釧路校准教授
早稲田大学教育・総合科学学術院准教授
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
古典学習論。近現代の国語教育史研究。教員養成における国語科教育法のあり方の検討。学習指導要領の分析。
◆主な著書・論文
『古典教育をオーバーホールする』(文学通信 2022年)
◆教員からの一言
国語科教育学を担当する菊野雅之です。国語の授業を作るためのとっかかりはどこにあるのか。言葉の力を育てるためには、どのような手だてが必要なのか。みなさん自身が、言葉の力を高めながら、その力を高める授業や手だてにはどのようなものが考えられるのか。それをともに議論していきたいと思います。
■教員紹介トップ
■教員紹介のページ(1)-上代/中古/近世/近代文学
■教員紹介のページ(2)-中国文学/日本語学/国語教育
■トップページへもどる