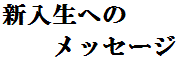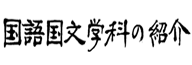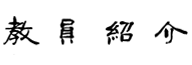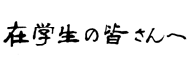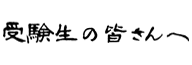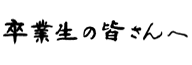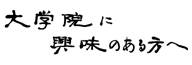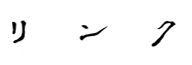■新入生へのメッセージ
早稲田大学教育学部国語国文学科に入学されたみなさま、ご入学おめでとうございます。
入学生のみなさまに先生方よりメッセージが届きました。ご一読ください。
(一部内容を編集・削除しました。ご了承ください 2014.11.13)
「机の上で本を読むこと」 石原千秋先生
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
みなさんの多くは、思わぬ形で長い「春休み」を過ごすことになるでしょう。その時間をどう過ごされますか?
皆さんが入学したのは早稲田大学教育学部国語国文学科です。言うまでもないことでしょうか。でも、皆さんの中にははじめからこの学科を志望してはいなかった方もおられるのではないでしょうか。実は、私は親の希望で、受験直前まで建築学科を志望していることになっていました。だから、小説は家でも授業中も(!)いつもいつも机の下で隠れて読んでいなければなりませんでした。もちろん、受験勉強はほとんどしませんでした。それが晴れて国文学科に進学したら、堂々と机の上で読んで良いことになったではありませんか。しかも、それが「勉強」だというのです。これには、自分で驚いてしまいました。
それが「勉強」だとすれば、私はまちがいなく大学時代にもっとも多く「勉強」しました。当時、新潮文庫で刊行されていた明治・大正期の小説はほとんど読みました。外国の小説も手当たり次第です。ドストエフスキーに圧倒されたロシア文学、スタンダールから恋を学んだフランス文学、ゲーテの教養はいやらしいなあと思ったドイツ文学、ディケンズにワクワクしたイギリス文学、ヘミングウェイの失われた世代を気取ったアメリカ文学。西洋哲学もギリシャ哲学からはじめて、当時は最先端だったフランスの現象学まで何とかたどり着きました。
もちろん、みんな忘れました。いや、忘れたと自分で思い込んでいます。それが勉強です。「プラトンの国家論は~」などと言っているうちは、まだチャート式の借り物の図式です。身についたときには、忘れてしまっているものです。そして、忘れるに値するのは古今東西の名作と言われる作品です。これから4年間(あるいはそれ以上)、皆さんは机の上で本を読んで、忘れる権利を獲得したのです。その権利を行使しない手はありません。たくさん本を読んで、フラフラになって4月にお会いしましょう。
「長編小説のすすめ」 金井景子先生
新入生のみなさん、
人生にはほんとうにいろんなことがあります。
私の教えている学生さんで、「ありえないよ!」というのが口癖の人がいるんですが、
その人が、「ありえないよ!」と口にするたびに、私は密かに、
『この子、人生で何回くらい、このことばを口にするかなあ』
と想像をめぐらせ、また、五十年以上生きて来た自分自身は、思考が止まるような驚きや悲しみ、憤りを何回くらいそのことばに代行させたかなあと考えます。
「ありえない」けれども、現実に起こっている。
文句を言っていれば済むうちはいいですが、そのことを受け止め、自分なりに咀嚼し、答えを出して、行動に繋げていかなければならないときが、人生には幾度もあります。
そうしたとき、あなたが柔軟で粘り強い思考を重ね、自身の思いを相手に届くことばで伝えたり、世界の片隅で上がっている消え入りそうな声を感知できる力を養うために、遠回りのように見えても、学ぶことには意味と希望があります。
このひと月、長編小説を読み通す経験にチャレンジしてみてはいかがですか?
たかが、小説。されど、小説。そこには人生のシュミレーションをするための、確かな小宇宙があります。
私のお勧めは、私が大学に入って最初に読んだ、
ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』です。
世界がいかに過酷で、猥雑で、不条理で、優しく、かけがえのないものであるかが解ります。
そして、生かされて在る素晴らしさも。
日本文学ならば、
島崎藤村の『夜明け前』でしょうか。
この作品を読んだのは、『カラマーゾフ・・・』の次でした。
大きな歴史の流れの中で、ほんとうに一人の人間はちっぽけだけれど、そのちっぽけな人間こそが舞台の裏側にいる、一人一人の思いを後世に伝えて行くんだと確信できました。
そこから始めて・・・
四月に、キャンパスでお目にかかったときに、その続きは直接、お話しします!