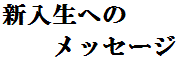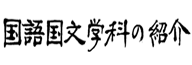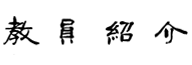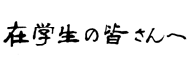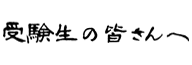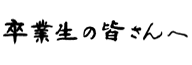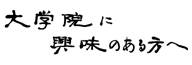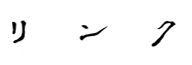■教員紹介(1)
上代文学
松本 直樹(まつもと なおき)
MATSUMOTO,Naoki
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
上代文学・日本神話
『古事記』『日本書紀』『万葉集』「風土記」
◆略歴
東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程退学。博士(文学)。
1991年、早稲田大学助手・非常勤講師。
1996年、日本学術振興会特別研究員PD。
2000年、早稲田大学専任講師。
2002年、同助教授(准教授)。
2008年、同教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
『古事記』『日本書紀』などの上代文献に収められた〈神話〉を中心に研究を進めてきました。神話とは本来、宇宙の起源や人の生死をも決定づける力をもって、人々に伝承されてきましたが、大和王権の手になった『記』『紀』、そして各国の「風土記」、また『万葉集』に収められている人麻呂らの歌は、〈神話〉という型を使って何を言わんとしたのか。7世紀から8世紀における〈神話〉という言説の意味を考えています。
◆主な著書
『古事記神話論』(新典社 2003年10月)
『出雲国風土記注釈』(新典社 2007年11月)
『神話で読みとく古代日本―古事記・日本書紀・風土記』』(筑摩書房、2016年6月)
『先代旧事本紀注釈』(花鳥社、工藤浩・松本弘毅と共著、2022年2月)
◆教員からの一言
平城京遷都から1300年が経ちました。この間、記・紀、万葉などの文学作品は、数えきれない多くの人々によって読み継がれ、また研究も続けられてきました。その後、現代に至るまでに書かれた多くの文学作品は、少なからず上代文学の影響を受けています。
歴史ある日本語日本文学の研究では、上代から近現代に至るまでの学問体系が築かれています。早稲田大学教育学部国語国文学科は、そうした学問体系のもとで研究・教育をすることが出来る体制を維持する、日本でも有数の学科であることを誇っています。
この伝統ある学科で、日本語日本文学を研究し、教育を通してそれを次代に継承することの喜びを感じながら、学んでほしいと思います。
中古文学
福家 俊幸(ふくや としゆき)
FUKUYA,Toshiyuki
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
平安時代散文学の研究
平安時代日記文学の研究
平安時代物語文学の研究
紫式部の研究
◆略歴
香川県に生まれる。桐蔭学園高校、早稲田大学教育学部卒業。
早稲田大学大学院文学研究科修士課程・博士課程修了。博士(文学)。
早稲田大学高等学院教諭、国士舘大学文学部助教授を経て、
2004年4月早稲田大学教育・総合科学学術院助教授、2008年4月教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
平安時代の散文学を中心に、研究を進めて来ました。現在関心があるのは、平安時代の日記文学とは何か、という問題です。
近代以降、平安時代の仮名日記は「私」の「文学」として読まれるようになりました。しかし「私」をあまりに重く考えて把握してしまったために、やや実態とは離れた、歪んだ享受となっている部分もあるように思われます。『紫式部日記』と『源氏物語』との関係や『更級日記』と『夜の寝覚』『浜松中納言物語』との関係などもあらためて考えてゆきたいテーマです。
◆主な著書・論文
『紫式部日記の表現世界と方法』(武蔵野書院 2006年9月)
「生徒の考える力を伸ばし、読みを深める古典教育」(「月刊国語教育」とうほう 2006年10月)
「『紫式部日記』と『栄花物語』との距離」(『栄花物語の新研究―歴史と物語を考える』新典社 2007年5月)
「『紫式部日記解』『紫式部日記釈』についての一考察」(『紫式部日記の新研究 表現の世界を考える』新典社 2008年5月)
「一条朝後宮から見た大斎院文化圏」(『王朝文学と斎宮・斎院』竹林舎 2009年5月)
「二つの大蔵卿正光-『枕草子』と『紫式部日記』」(『日記文学研究 第三集』新典社 2009年10月)
◆教員からの一言
2008年は源氏物語千年紀でした。源氏物語に関するイベントが各地で開催され、源氏物語に熱い注目が集まりました。本当に源氏物語が読まれていたのかといえば疑問ですが、それにしても源氏物語は千年の時を超えて現代人の心を揺すぶる力を持っているのです。平安時代の文学作品には他にもそうした力を持った作品がたくさんあります。教場でお会いできる日を楽しみにしています。
新美 哲彦(にいみ あきひこ)
NIIMI, Akihiko
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
『源氏物語』を中心とした平安時代散文学の中近世から現代にいたる受容の研究
◆略歴
東京都出身。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。
早稲田大学大学院文学研究科修士課程・博士課程修了。博士(文学)。
2004年、呉工業高等専門学校講師。
2008年、ノートルダム清心女子大学講師。
2009年、同大学准教授。
2014年、早稲田大学教育・総合科学学術院准教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
平安・鎌倉時代に作成された物語について、江戸時代に至るまでの受容の歴史も含めて研究しています。比較によりあらわれる差異を見ていくことが好きなので、物語や古注釈の諸本の研究を中心に行っていましたが、古注釈を作成した場の問題や、江戸時代の物語享受、特に、物語関係の板本の挿絵などにも興味を持ちつつあります。
◆主な著書・論文
『源氏物語の受容と生成』(武蔵野書院 2008年9月)
共編著『『源氏物語』の近世―俗語訳・翻案・絵入本でよむ古典―
「『我が身にたどる姫君』の成立過程再考」(『国語と国文学』9
「新出「若紫」巻の本文と巻末付載「奥入」 ―定家監督書写四半本『源氏物語』との関係を中心に」(『中古文
「豊臣秀吉と『源氏物語』」(『日本古典文学を世界にひらく』勉
「『言経卿記』に見る女性たちの文学作品享受――西御方(祐心尼
◆教員からの一言
文学を含めた文化の世界は豊饒です。しかし文化はもろいものでもあります。実際に、平安・鎌倉時代の物語のほとんどは散佚してしまっています。近い例でいえば、漫画の『サザエさん』に書き込まれる縁台将棋、縁側での団欒のような文化は、日常生活の中ではもうほとんど見られません。意識的に維持しなければ消えてしまう文化も多いのです。文学研究において、『源氏物語』の中世や近世における受容を考えること、「古典」作品がどのように書写され受け継がれたかを調査すること、これは文化の多様性の「発見」です。これらの研究を継続することによって、文化の多様性は、日々更新されていきます。豊饒な文化を維持し、文化の多様性、重層性を更新すべく、ともに学んでみませんか。
中世文学
海野 圭介(うんの けいすけ)
UNNO,Keisuke
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
日本中世文学・和歌文学・日本古典籍書誌学
王朝古典や和歌の注釈活動・伝授等の古典学の研究
中世の宗教文学・寺院資料の研究
◆略歴
静岡県出身。大阪大学文学部国文学科卒業。
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。
2000年、日本学術振興会特別研究員。
2002年、大阪大学文学部助手。
2007年、ノートルダム清心女子大学講師、同准教授。
2010年、国文学研究資料館准教授、同教授。
2010年、総合研究大学院大学准教授、同教授(併任)。
2024年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
日本中世の文学や思想が生み出されるメカニズムに関心があり、和歌や散文文芸、思想・信仰のテクストを生み出した人々が、何を学び、どのようにしてそれを作り上げたのかという創造の秘密の解明をめざして検討を重ねて来ました。具体的には、中世に行われた学問の在り方や知識の蓄積と流通の実態を伝える資料の発掘とその読み解きを通して研究を進めています。文学や思想を書き留めた書物それ自体を研究対象とする古典籍書誌学、研究成果やデータの新たな活用方法を模索するデジタルヒューマニティーズの領域にも関心があります。
◆主な著書・論文
『国立歴史民俗博物館資料目録[8-1] 、[8-2]高松宮家伝来禁裏本目録 [分類目録編]、
[奥書刊記集成・解説編]』(国立歴史民俗博物館、2009年)(分担執筆)
『天野山金剛寺善本叢刊 1~5』(勉誠出版、2017年~2018年)(共編著)
『和歌を読み解く 和歌を伝える―堂上の古典学と古今伝受』(勉誠出版 2019年)(単著)
『寺院文献資料学の新展開4、5』(臨川書店、2020年、2022年)(分担執筆)
『本 かたちと文化』(勉誠出版、2024年)(分担執筆)
◆教員からの一言
平安時代に著された王朝文学は、後の時代には「古典」として読み継がれ、新たな作品を生み出す知識基盤となりました。その理解や解釈には時代の価値観や信仰が色濃く反映していて、仏教や神道、儒学思想などを取り込みつつ展開しました。例えば、『源氏物語』の作者・紫式部が絵空事の物語を著した罪によって地獄に落ちたという話は、中世においてはある種の常識でした。式部の魂を救うために源氏供養という儀礼が生まれ、そのテーマは能としても再生します。古典とは遠い昔の閉じられた作品ではなく、それぞれの時代を生きる人々によって絶えず再構築されてきました。そうした古典の意義や意味を考えながら、日本古典の面白さを見出して行きたいと思っています。皆さんと共に学び、考える時間と場を共有できることを楽しみにしています。
田渕 句美子(たぶち くみこ)
TABUCHI,Kumiko
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
鎌倉時代の和歌と歌人の研究
鎌倉時代の日記文学の研究
鎌倉時代の文化・学芸の研究
中世の女房とその文学の研究
◆略歴
東京都出身。お茶の水女子大学卒業。同大学院修了。
1991年、大阪国際女子大学専任講師。
1994年、大阪国際女子大学助教授。
1998年、国文学研究資料館助教授。
2002年、同教授。
2008年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
中世和歌文学を専門としていますが、中世文学全般にわたって関心があります。作者の一人一人が、中世という転換期の時代にあって、どのように生き、どのような和歌を詠み、作品を書き、それがどのような意味を持っていたのかを、明らかにする研究を行ってきました。現在は特に、女房が詠んだ和歌、女房が書いた文学全般に興味を持っています。女房とは、宮廷におけるキャリアウーマンであり、文化的に大きな役割を果たしていました。文化発信者としての女房について、できるだけ新しい視点から考えたいと思っています。
◆主な著書・論文
『中世初期歌人の研究』(笠間書院 2001年)
「『新古今和歌集』の成立―家長本再考 」(『文学』8巻1号 岩波書店 2007年 1月)
『阿仏尼』(吉川弘文館 2009年)
『新古今集 後鳥羽院と定家の時代』(角川選書 2010年)
『異端の皇女と女房歌人―式子内親王たちの新古今集』(角川選書 2014年)
『女房文学史論―王朝から中世へ―』(岩波書店 2019年)
『百人一首―編纂がひらく小宇宙』(岩波新書 2024年)
◆教員からの一言
和歌は、千年以上にわたって日本文学を貫流する文学です。世界にも類を見ない短詩型文学であると同時に、現代のメールにも通じる、コミュニケーションの手段でした。巧みな本歌取りをした奥深い和歌もあれば、軽やかな戯れの和歌もあります。また和歌は、日記や物語など、さまざまな文学の要所にあります。時代をさかのぼって旅しながら、その多様な魅力を発見していきましょう。
近世文学
天野 聡一(あまの そういち)
AMANO,Soichi
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
和学者による和文小説創作
近世中後期の上方における学問と文学
◆略歴
兵庫県明石市出身。神戸大学文学部卒業。同大学院修了。
神戸大学大学院人文学研究科修了。博士(文学)。
2007年、日本学術振興会特別研究員DC1。
2011年、日本学術振興会特別研究員PD。
2012年、九州産業大学専任講師。
2016年、九州産業大学准教授。
2023年、九州産業大学教授。
2024年、早稲田大学教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
卒業論文で取り組んだのは上田秋成の『雨月物語』でした。大学院進学後、秋成を含む複数の和学者が、古典文学から語句や表現、構成などを借りて様々な小説を創作していたことを知り、それ以来、江戸時代における学問的営為(注釈)と創作的営為(小説)の関係について関心を抱き続けています。
◆主な著書・論文
『藤原定家と式子内親王:恋物語の生成と展開』(新典社、2025年4月)
『近世和文小説の研究』(笠間書院、2018年12月)
『三弥井古典文庫 雨月物語』(共編、三弥井書店、2009年12月)
◆教員からの一言
近世文学研究は、限られた資料から作品や言説が世に出された経緯を推理・実証していく非常にスリリングな行いであり、なおかつ、人間の内面に深く立ち入る学問です。たとえば、ある作品のある場面が生み出された経緯を知るためには、その作品の構成を分析することはもちろん、当時の時代状況や思想・文学の潮流、書き手の社会的立場や実人生、さらには書き手が参照したであろう先行作品や史実も調べておく必要があります。こうした調査を重ねるなかで、皆さんは過去の歴史や、そこに生きた人々の様々な振る舞いを知ってゆくことでしょう。近世文学研究に真摯に打ち込んで得られるものは、決して表面的な知識だけではなく、人間および文化全般に対する深い洞察力と複眼的な物の見方であるはずです。皆さんとともに学びを深めてゆくことを楽しみにしています。
近代文学
石原 千秋(いしはら ちあき) ISHIHARA,Chiaki
ISHIHARA,Chiaki
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
夏目漱石の文学を中心とした近代文学
テクスト論の立場から、多くの小説を論じる
国語教科書の言説分析
入試国語の研究
◆略歴
成城大学卒業、同大学院文学研究科博士課程後期中退。
1983年、東横学園女子短期大学専任講師。
1993年、成城大学助教授。
2003年、早稲田大学教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
これまで、漱石文学を中心に論じてきました。文学理論にも関心があり、「作者」の問題を論の中に入れない「テクスト論」という立場によって、村上春樹文学、ケータイ小説など様々な文学からJポップまで、活字なら何でも論じてきました。現代文学にも関心を持ち続けたいので、「文芸時評」も続けてい ます。また、同じような立場から国語教科書や入試国語についても論じてきました。
これからも何でも論じるでしょうが、ライフワークは江藤淳の名著『漱石とその時代』の向こうをはって『時代の中の漱石』を書くことです。また、文学理論の中では特に「読者」に関心があります。『テクスト論の感性』、『テクスト論の方法』、『テクスト論の思想』の「テクスト論」三部作を完成させることも夢です。
◆主な著書・論文
『反転する漱石』(青土社 1997年)
『教養としての大学受験国語』(ちくま新書 2000年)
『テクストはまちがわない』(筑摩書房 2004年)
『漱石と三人の読者』(講談社現代新書 2004年)
『国語教科書の思想』(ちくま新書 2005年)
『百年前の私たち』(講談社現代新書 2007年)
『謎とき 村上春樹』(光文社新書 2007年)
『国語教科書の中の「日本」』(ちくま新書 2009年)
『名作の書き出し 漱石から春樹まで』(光文社新書 2009年)
『あの作家の隠れた名作』(PHP新書 2009年)
『漱石はどう読まれてきたか』(新潮選書 2010年)
『『こころ』で読みなおす漱石文学 大人になれなかった先生』(朝日文庫 2013年)
『漱石入門』(河出文庫 2016年)
『読者はどこにいるのか 読者論入門』(河出文庫 2021年)
『教科書の中の夏目漱石』(大修館 2023年)
◆教員からの一言
大学では「自由に読むこと」の楽しさと厳しさを学ぶことになるでしょう。大学で「自由に読むこと」は、「ふつうの読み方」でない個性的な読み方を見つけ、さらに、その個性的な読み方に何らかの「根拠」を示し、教室の仲間を説得しなければなりません。自分の「個性」を見つめ、それを文学の「読み」を通して他人に認めてもらうこと。それは楽しくまた厳しい「仕事」です。それにチャレンジする人を、大学は待っています。
金井 景子(かない けいこ)
KANAI,Keiko
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
ジェンダー論の研究
朗読を機軸とした音声言語教育の研究
◆略歴
大阪府に生まれる。山崎学園富士見中学・高等学校、早稲田大学文学部卒業。
早稲田大学大学院文学研究科修士課程・博士課程修了。
亜細亜大学助教授を経て、
1999年、早稲田大学教育・総合科学学術院助教授。
2005年、教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
私がこれまで研究対象にしてきたのは、
1.正岡子規を視座とした1900年前後の文学状況
2.川端康成を視座とした1920年代から1940年代の文学状況
3.樋口一葉、与謝野晶子、幸田文をはじめとする、日本の近・現代女性作家
です。
対象に応じて、作家研究、作品研究、メディア研究を展開しています。
現在、最も関心があるのは、石牟礼道子の『苦海浄土』を視座として水俣病問題を考えることです。
また、私のホーム・ページのキャッチ・フレーズ「文学・教育・ジェンダーの交差点」に集約されるように、文学作品を題材にしながら、
1.教育におけるジェンダー
2.朗読を中心とした音声言語教育
に取り組んでいます。論文執筆に加えて、さまざまなイベントも行っていますので、オリジナル・サイトをご参照ください。
◆主な著書・論文
編著『女子高生のための文章図鑑』(筑摩書房、1994年)
編著『男子高生のための文章図鑑』(筑摩書房、1997年)
編著『幸田文の世界』(翰林書房、1998年)
編著『ジェンダー・フリー教材の試み――国語にできること』(学文社、2001年)
編著『正岡子規集』(岩波書店、2003年)
編著『声の力と国語教育』(学文社、2007年)
編著『女学校と女子教育』(ゆまに書房、2009年)
『真夜中の彼女たち――書く女の近代』(筑摩書房、1995年)
「耳で読む/目で聴くためのレッスン――朗読教育のために考えておきたいこと」
(『早稲田大学国語教育研究』、2002年3月)
「「文学作品」がジェンダー・フリー教材になるとき」(『季刊 文学』、2002年11月)
「「償い」を問う――「水俣病」と『苦海浄土』の半世紀」(『学術研究』、2009年3月)
◆教員からの一言
私は、学生の頃から、「文学作品を通して、歴史の波間に浮き沈みする人や自然の声を聴くこと」を無上の喜びと感じて、読んだり書いたりしてきました。幼い頃から、生活環境が大きく変わる体験を重ねてきたことも、多方面の分野に関心を向ける要因になっていると思います。「豊かさ」や「美しさ」、「正しさ」の基準はひとつではありません。学び続けると、それが少しずつ見えてきます。
◆教員オリジナルサイト
金井景子研究室ホームページ
五味渕 典嗣(ごみぶち のりつぐ)
GOMIBUCHI,Noritsugu
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
近現代日本語文学・文化研究
近代日本における戦争文学と文化表象の研究
◆略歴
栃木県出身。慶應義塾大学文学部文学科国文学専攻卒業。
慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。
2001年、中央大学附属高等学校教諭。
2006年、大妻女子大学文学部専任講師。同准教授、同教授を経て、
2019年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
谷崎潤一郎、夏目漱石、坂口安吾、保田與重郎といった書き手の仕事を中心に、文学や文化を広く時代の中の表現と捉える立場から、ことばに刻まれた思考や歴史の痕跡をたどり直す研究を行ってきました。
近年は、日中戦争期・アジア太平洋戦争期の戦争文学や従軍体験記・ルポルタージュに注目、戦争の時代を生きた人々がどんな戦争や戦場のイメージと接していたのか、戦時体制期の軍や政府がメディアや表現をどのように規制したかを追いかけています。同じ問題意識から、戦後日本社会の中での「戦争の記憶」にも関心を持って勉強を続けています。将来的には、このテーマで「近代日本戦争文学史」を書き上げることが目標です。
◆主な著書・論文
単著『言葉を食べる 谷崎潤一郎、1920~1931』(世織書房 2009年)
共編『高校生のための現代文ガイダンス ちくま評論文の読み方』(筑摩書房 2016年)
共編『漱石辞典』(翰林書房 2017年)
単著『プロパガンダの文学 日中戦争下の表現者たち』(共和国 2018年)
単著『「国語の時間」と対話する 教室から考える』(青土社 2021年)
単著『「敗け方」の問題 戦後文学・戦後思想の原風景』(有志舎 2023年)
◆教員からの一言
文学や文化の勉強は、すぐに結果が出るものでも、明快な答えが出るようなものでもありません。むしろ、「答え」として示された中身を吟味し、なぜそれが「答え」になりうるのか、それを「答え」として成り立たせるにはどんな前提や条件が必要なのか、そのうえで自分はどの「答え」を選び、他者に向けて表現していくかを考えるものだと思っています。だから、文学や文化を学んで見えてくる「答え」は、決してひとつにはなりません。それこそまさに、文学や文化の「豊かさ」だと私は思います。
これまで「文学」として書かれ、読まれてきたことばの中には、それぞれの時間を生きた先人たちの生と声とが、ときに生々しく、ときにひそやかに刻みこまれています。ひとがひとりで考えられることはそれほど多くありません。時代の中で書かれながら、時代を超えて出会うことができるさまざまなことばのざわめきに耳を澄ませ、教室の内と外で「共に考える」空間を作り上げていきたいと考えています。
和田 敦彦(わだ あつひこ)
WADA, Atsuhiko
教育・総合科学学術院 教授
◆専門分野
日本近現代文学
近代読書論・読者論
メディア論
出版史、蔵書史等のメディア史研究
◆略歴
高知県出身。早稲田大学卒業、同大学院修了。博士(文学)。
1996年、信州大学人文学部助教授。
2007年、早稲田大学教育・総合科学学術院准教授。
2005年3月~翌年1月、コロンビア大学客員研究員。
2008年、早稲田大学教育・総合科学学術院教授。
◆これまでの研究内容・現在関心のあるテーマ
日本近代文学を専門としていますが、明治期の新聞、雑誌から現代のビデオゲームまで、広く近代現代の表現について関心をもって研究してきました。文学研究というと、作家やその作品の研究が思い描かれがちですが、読書や読者の歴史、さらには出版や書物の流通に関しても関心をもっています。また、海外における日本語蔵書の歴史も調査してきました。
◆主な著書・論文
『読むということ』(ひつじ書房 1997年)
『読書論・読者論の地平』(若草書房 1999年)
『メディアの中の読者』(ひつじ書房 2002年)
『書物の日米関係』(新曜社 2007年)
◆教員からの一言
読者や読み、書く能力の歴史に関心があります。こうした能力は、私たちが日々考え、生きるために必須の力です。表現や、読者の歴史に幅広く関心を持つことが、現代の私たちをとりまく情報環境を批判的にとらえるための鍵になると思っています。皆さんには何よりも日本の近代に生まれたいろいろな資料に出会ってほしい、そんな機会を少しでも作っていきたいと思っています。
それと、学生達と飲みに行くことを大事にしています。
◆教員オリジナルサイト
和田敦彦研究室ホームページ
■教員紹介トップ
■教員紹介のページ(1)-上代/中古/近世/近代文学
■教員紹介のページ(2)-中国文学/日本語学/国語教育
■トップページへもどる